【開催報告】アルザス欧州日本学研究所主催・法政大学国際日本学研究所共催・東芝国際交流財団後援 第3回国際シンポジウム「多文化共生と今後の日本社会-北と南の比較から考える」(2025年3月14日~16日)2025/03/31
アルザス欧州日本学研究所(CEEJA)主催
法政大学国際日本学研究所(HIJAS)共催
東芝国際交流財団 (TIFO)後援
“NORTHERN LIGHTS 3: Cultural Coexistence and the Future of Japanese Society
A Comparative Perspective from North to South”
(多文化共生と今後の日本社会-北と南の比較から考える)
第3回 国際シンポジウム 開催報告
去る2025年3月14日~16日、フランス・アルザスにおいて標記の国際シンポジウムが開催された(対面とZoom 利用によるHybrid-Flexible形式)。これはCEEJAが「日本における地方の魅力」というテーマで、(公財)東芝国際交流財団(Toshiba International Foundation=TIFO)の助成(2022年3月決定)を得て行われたものの第三回目の国際シンポジウムである。第1回、第2回に続き今回も、企画段階からHIJASが全面的に協力して構成した。第1回は古代・中世に視点を当て、第2回は続く近世という時代に視点を当てたが、最終回となる第3回は近現代を中心に扱った。
日本の地方の扱い方にはいろいろな切り口があるが、このシリーズでは焦点を北に当てて、日本史における北の地方について解説してきたが、その様相をより明確にするために、今回は南のもう一つの「日本」(北と合わせて、もう二つの「日本」)である琉球・沖縄も比較のため取り上げた。
Scientific Committeeは、小口雅史(HIJAS)、François LACHAUD(フランス国立極東学院(EFEO) )、Virginie FERMAUD(CEEJA)の3名。第3回のタイトルはNORTHERN LIGHTS 3 : Cultural Coexistence and the Future of Japanese Society: A Comparative Perspective from North to South。邦題は「多文化共生と今後の日本社会-北と南の比較から考える」とさせていただいた。
14日に開会セレモニーがPalais de l’Europe(Le Conseil de l’Europe, Strasbourg。ヨーロッパ評議会)Salle n°10で行われた(写真1)。
 (写真1)ヨーロッパ評議会内会議室 (左より)HIJAS客員所員・北海道大学大学院文学研究院教授 谷本晃久氏 |
まず開会の挨拶が行われ、CEEJA所長のCatherine TRAUTMANN氏、(公財)東芝国際交流財団専務理事の山崎裕紀氏、HIJASの小口、EFEOのFrançois LACHAUD氏の順に祝辞が述べられたが、小口は加えて、TIFOへの謝辞と今回のシンポの意義と内容についても概括的に触れた。
そのまま基調講演へと移り、HIJAS客員所員・北海道大学大学院文学研究院教授の谷本晃久氏より、全体のタイトルと同じ “Cultural Coexistence and the Future of Japanese Society: A Comparative Perspective from North to South” と題して行われた(写真2)。続けてLACHAUD氏の”Beyond Mingei: Yanagi Muneyoshi, Ainu Culture, Northern Worlds” と題する基調講演が行われた。これまで同様、素晴らしい国際会議場での盛大な開会式となり、各方面にも好評であったとのことである。
午後から個別研究報告に入った(司会はRegine MATHIAS, CEEJA副所長)。佐々木史郎氏(HIJAS客員所員・国立アイヌ民族博物館館長)より、カラフトナヨロ惣乙名文書から読み取れるカラフトアイヌの近世・近代史をめぐる報告が行われて初日を終えた(写真3)。
 (写真2)HIJAS客員所員・北海道大学大学院文学研究院教授 谷本晃久氏 |
 (写真3)HIJAS客員所員・国立アイヌ民族博物館館長佐々木史郎氏(ZOOM) |
翌15日からは、会場をColmarのCEEJAに移して開催され(写真4)、沖縄と北海道を対比する報告を中心に行われた(司会は引き続きMATHIAS氏)。上江洲安亨氏((一財)沖縄美ら島財団首里城公園管理センター首里城事業課副参事)による御後絵(国王肖像画)復元模写に関する研究(Zoom)、大里知子氏(法政大学沖縄文化研究所准教授・専任所員)による近代以降の首里城をめぐる歴史研究(Zoom)、宮里正子氏(浦添市美術館元館長)による琉球漆器研究(写真5)、浅倉有子氏(上越教育大学名誉教授)によるアイヌ漆器研究(写真6)、堀川三郎氏(HIJAS兼担所員、法政大学社会学部教授)による小樽を中心とした近代北海道の開発と再開発をめぐる研究(写真7)が続いた。
 (写真4) 2025年3月15日・16日 会場:CEEJA施設内 |
||
 (写真5)宮里正子氏 |
 (写真6)浅倉有子氏 |
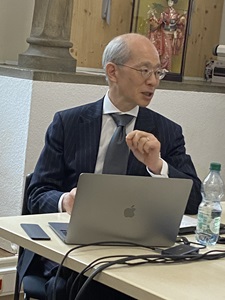 (写真7)堀川三郎氏 |
16日は司会を小口に交代し、佐々木利和氏(HIJAS客員所員、北海道大学アイヌ・先住民センター招へい教員)による東京国立博物館とベルリン国立民族学博物館の琉球文化財の研究(Zoom)、松本あづさ氏(HIJAS客員所員、藤女子大学准教授)による北海道出身の大学生と北海道史・アイヌ史めぐる実態研究(Zoom)と続き、最後を、自身がアイヌである野本正博氏(民族共生象徴空間運営本部副本部長)による「この土地の伝承、コタンからウポポイへ」で締めくくった(写真8)。第3回報告者全員による相互コメントの後、小口が三年間を振りかえって総括した。
 (写真8) 民族共生象徴空間運営本部副本部長 野本正博氏(左)/小口雅史(右) |
またシンポジウム終了後、現地報告者一行は、小口の引率のもと、ドイツのベルリンに赴き、Ethnologishe Museum Berlin(案内はHenriette Lavaulx-Vrècourt氏)、Museum für Asiatische Kunst(Humnoldt Forum、案内はAlexander Hofmann氏)の収蔵庫内を見学することができ、多くの成果を挙げることとなった。案内の労を執ってくださった両氏に末尾ながら厚く謝意を表したい。
【執筆:小口雅史(国際日本学研究所兼担所員・法政大学文学部教授)】

