【開催報告】「トランスナショナルな日本」研究会(7) 「日本のスポーツとトランスナショナリズム」(2025年10月4日(土))2025/10/20
【開催報告】「トランスナショナルな日本」研究会(7)
「日本のスポーツとトランスナショナリズム」
■ 日時:2025年10月4日(土)14時~16時45分
■ 会場:法政大学市ヶ谷キャンパス 大内山校舎6階 Y605教室 【対面+オンラインで開催】
■主催:法政大学国際日本学研究所
■ 報告者:松山 啓(法政大学 国際日本学研究所 客員学術研究員)
■ 報告者:北原 卓也(早稲田大学 人間科学部講師)
■ コメンテーター:鈴村 裕輔(名城大学 外国語学部教授、法政大学 国際日本学研究所 客員所員)
■ 司会:山本 真鳥(法政大学 名誉教授・国際日本学研究所 客員所員)
国際日本学研究所では、「トランスナショナルな日本」という視点から、国内外で研究会を開催してきた。今回は、「日本のスポーツとトランスナショナリズム」をテーマに、日本に中心があり日本のしきたりや文化に外国人が参入する形でトランスナショナル化が進んできた相撲と、早くから外国人選手を取り込んでトランスナショナル化を進め強化に努めてきたラグビーを好対照に取り上げて、人類学を専門とする研究者2名による研究報告を行った。
まず、司会の山本真鳥氏(法政大学 名誉教授・国際日本学研究所 客員所員)から、本研究会の主旨について、スポーツをテーマとしたトランスナショナリズムに関する話題が提供された。その後、松山啓氏(法政大学 国際日本学研究所 客員学術研究員)が、「大相撲の国際化/多国籍化と部屋制度」と題する報告を行った。松山氏は江戸時代から現在に至る相撲興行と部屋制度の成立過程を概観しながら、大相撲の興行体制とナショナリズムの不可分な関係性を指摘した。そのうえで、これまで大相撲に携わってきた外国出身力士のトランスナショナルな動向を通覧しながら、その背後にある社会情勢の変化や様々な仲介者の存在を提示した。そのなかでも、近年のアマチュア相撲の国際化と国内における競技人口の減少、大相撲の大卒出身関取の増加傾向が、従来の部屋制度を変革する潜在性を孕んでいる点が示唆された。最後に、今後の興行体制について、アマチュア相撲との一層の差別化を図る保守的な「国技」路線を維持するのか、それとも外国籍枠の見直しを含めた多国籍化の促進と文化的装飾の維持の両立を目指すのか、といった選択を迫られる大相撲の未来が語られた。
次に、北原卓也氏(早稲田大学 人間科学部講師)から「日本のラグビー界に貢献するトランスナショナリズム」と題する報告が行われ、日本で活躍するトンガ人のラグビー選手の事例を中心としたトランスナショナリズムの展開が提示された。まず北原氏は、ラグビーが国際スポーツとして成立するまでの歴史的な過程を示しながら、プロ化による選手のトランスナショナルな移動が活発化した背景を提示した。特にトンガ人選手にとっての国際的な移籍には、経済的成功の手段としての側面が見出されることや、キャリア形成に介在する多様な仲介者やエージェントの役割が示された。また、日本におけるトンガ人選手の暮らしや、不安定な雇用事情、日常生活をめぐる困難が具体的な事例を交えて取り上げられた。最後に、代表資格やリーグの規定に伴い、彼らが戦略的な国籍変更を行っていることや、世代の移り変わりや雇用形態等の時代的・制度的変化に翻弄されながらも、その都度適応を試みるトンガ人選手のラグビーを通じたトランスナショナルな生き方が示唆的に示された。
その後、今回のコメンテーターである鈴村裕輔氏(名城大学 外国語学部教授、法政大学 国際日本学研究所 客員所員)から、2名の報告者に対するコメントが行われた。そこでは、国内のアマチュア相撲における競技人口が低迷し、大卒力士が増加する大相撲は、トランスナショナルな移動を含めた豊かな背景をもつ様々なタイプの力士をどのように確保していくべきなのか、ラグビーにおける選手層の薄さと外国人選手起用の活性化がどのように関わっているのか、さらに両報告に対する共通の問いとして、観るものとしての大相撲・ラグビーという興行やスポーツで想起される「あるべき姿としての大相撲・ラグビー」像が、トランスナショナリズムにどのような影響を与えるのか、といった問いが提示された。松山氏は、アマチュア相撲の国際化と大相撲における「相撲」の差異をめぐるやりとりが、多様な力士を育む契機となる可能性や、大相撲に対する理想が郷土力士への期待を背景として現れる点を指摘した。また、北原氏からは、ラグビー界の「国籍」に対する認識について、ラグビーファンの言説としての「日本人」像が、血統主義に基づいた認識に近く、他国の場合は、あくまでも行政上のシステムにおけるラベル的な認識といった立場の違いによる捉え方の相違があるのではないか、といった意見が提示され、研究会全体を通して、オンライン参加者からの質問やフロアからの議論も活発に交わされた。
【執筆者:松山啓(法政大学国際日本学研究所客員学術研究員)】
 報告者1:松山啓氏 |
 報告者2:北原卓也氏 |
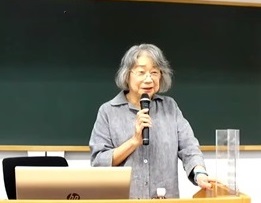 司会:山本真鳥氏 |
 コメンテーター:鈴村裕輔氏 |

