【開催報告】「トランスナショナルな日本」研究会(6) 『ベン・ブラッドリー自伝』刊行記念 「『ワシントン・ポスト』編集主幹のベン・ブラッドリーと日米ジャーナリズム考」(2025年6月21日(土))2025/10/20
【開催報告】
「トランスナショナルな日本」研究会(6)
『ベン・ブラッドリー自伝』刊行記念
「『ワシントン・ポスト』編集主幹の
ベン・ブラッドリーと日米ジャーナリズム考」
■ 日時:2025年6月21日(土) 14時30分〜16時30分
■ 会場:法政大学市ヶ谷キャンパス 大内山校舎5階 Y506教室【対面式で開催】
■ 主催:法政大学国際日本学研究所
■ 報告者:根津 朝彦(立命館大学産業社会学部教授、法政大学国際日本学研究所客員所員)
■ コメンテーター:田中 優子(法政大学名誉教授・国際日本学研究所客員所員)
■ 司会:髙田 圭(法政大学国際日本学研究所准教授)
去る6月21日、法政大学市ヶ谷キャンパスにて法政大学国際日本学研究所主催の研究会「『ワシントン・ポスト』編集主幹のベン・ブラッドリーと日米ジャーナリズム考」が開催された。日本ジャーナリズム史の専門家で国際日本学研究所客員所員の根津朝彦氏は、この度アメリカ人ジャーナリスト、ベン・ブラッドリー(1921〜2014)の自伝の翻訳書(共訳)を法政大学出版局から出版した。国際日本学は、日本の文化・社会・政治を世界との比較やつながりから見ていくものであり、今回はアメリカ・ジャーナリズムの理解を通じて日本のジャーナリズム文化やその課題を考えることを主題とした。こうした目的から、コメンテーターとして長年マスメディアで積極的に発言されてきた田中優子氏を招き、現場からの経験を踏まえて根津氏への報告と日本ジャーナリズムへの意見を伺うことにした。
研究所所長の横山泰子氏によるあいさつの後、まず根津氏から本書出版の経緯と概要についての説明がなされた。今回の出版の背景の一つに根津氏がウォーターゲート事件を描いたジャーナリズム映画の名作『大統領の陰謀』を観たことがきっかけであったという。その後、共訳者とともにじっくりと翻訳を進め、この度その成果がようやく実を結び出版へと至った。本書は、ブラッドリーの生い立ち、小さな地域紙の駆け出しの記者からフランスでの大使館報道員、『ニューズ・ウィーク』特派員などを経て『ワシントン・ポスト』の記者となり、ニクソン大統領の政治スキャンダルであるウォーターゲート事件に編集主幹として立ち向かう時期を黄金期として生涯全体を描いた500頁近くの大著となっている。こうした激動のジャーナリスト生活に加えて、事実を重んじるジャーナリストによる自伝ならではのケネディ大統領との交友や三度の結婚などプライベートの面も赤裸々に記されており、読み応えがある。ブラッドリーという一人のジャーナリストの生涯からさまざまに戦後のアメリカ・ジャーナリズムの制度や文化を知ることができる本書は、根津氏が講演の中で指摘したとおり、アメリカ本流のジャーナリズム史を学べる日本語での書籍は少ないこともあり、非常に貴重な成果となっている。
翻訳者である根津氏が考える本書が持つ最大のメッセージは、いかに言論圧力に屈しないかというジャーナリストとしての気概とジャーナリズムの文化である。根津氏は講演の中でブラッドリーが編集主幹として権力に屈せずウォーターゲート事件を報道し続けたことの意義を訴えた。実際にこれまでのご自身の戦後日本ジャーナリズム史研究の中で根津氏は権力による言論圧力を一つの軸として研究を進めてきた。戦後日本のジャーナリズムにおいて「日本の編集幹部の言論圧力への抵抗の弱さ」が目につくという。こうした視点から、その後の講演では日本のジャーナリズム文化の課題へと話題が発展していった。ここで取り上げられた問題の一つに「中立信仰」がある。曰く日本のジャーナリズムには「異様なほどに(政治的主張が)偏ることへの恐れ」があるという。多くのメディアはこうした「中立」という立場が権力側を利することを十分に理解していない。ジャーナリズムは「ファクト」を報道することが主であるが、それと同時にメディアには「論説」や「オピニオン」を提示する役割がある。根津氏は、大学時代に薫陶を受けた田中優子氏の「しっかり自分の意見を伝えることだけが頭にあります」という『朝日新聞』でのインタビューを紹介し、意見を述べていくことの重要性を訴えた。
講演後、田中優子氏によるコメントが述べられたが、その内容の多くは、こうした根津氏による「熱のこもった」メッセージに応えるものであった。田中氏が法政大学で担当していた比較文化論の授業では、必ず「新聞の歴史」という回を設けていたというエピソードに触れ、日本の新聞が瓦版という形で欧米とほぼ同時期に生まれたにもかかわらず、その後の幾度の大戦の中で新聞が抵抗のためではなく政府のために役割を果たしてきた残念な歴史があると説明された。その上で、日本のメディアでは政府の重要な秘密などを暴いたりすると、そのジャーナリストがさまざまにメディアを通じて「叩かれる」ということが起きてきたと述べた。それは、1971年の沖縄返還協定の機密を報道した沖縄密約事件から、近年では、2014年から15年にかけて生じた安倍政権による報道テレビ番組への介入・圧力まで、現代的な問題としても存在し続けている。こうした状況の中で、ブラッドリーの気骨ある権力への抵抗には学ぶべき点が少なくないとコメントされた。
それでは、こうした課題を少しでも改善していくためにはどうすればよいか?根津氏、田中氏がともに強調したのは、教育の重要性であった。根津氏は「日本の教育ではジャーナリズムのポジティブな役割を学ぶ機会が極端に少なく」、むしろ「マスゴミ」といったようにジャーナリズムをたたく風潮が強まりつつある傾向への危惧を訴えた。これにはジャーナリズムの担い手たち自身がもっとジャーナリズムの重要性と魅力を伝えていく必要があり、「憧れる」仕事として認知されるための努力が必要だという。こうした論点に対して、田中氏も大学においてジャーナリズム学科といったプロフェショナルを養成する場が必要なのではないかとジャーナリスト教育の重要性に同意を示した。その上で、YouTubeなどの新しいメディア、また地方紙などマスメディアの周辺においてはジャーナリズム精神が息づいた報道がなされているとメディア環境に暗雲が立ち込める中、明るい展望の可能性が示された。
ベン・ブラッドリーの自伝を出発点とした日本のジャーナリズム文化をめぐる議論は、その後予定の時間を大幅に超過して、フロア参加者を交えた活発な議論が展開された。そこで、ジャーナリズムの課題とは別に、日本の出版に関わる重要な論点も提示された。横山泰子氏は、以前は欧米の重要な文献が多く翻訳されていたが、近年は研究書の出版がどんどんと減っている状況の中で貴重な仕事であると述べた。確かにオンライン上では日本国外の情報を容易に手に入れることができるようになった反面、人文社会科学ではむしろ国外の状況にアクセスしにくい状況が生じてきている側面もある。それは個々人が英語をはじめとした外国語で書かれた情報をじかに取得する要請が高まっているということを意味するが、現実的には、翻訳の減少によって人文社会科学の知がうちに封じ込められてしまっている状況にもつながっている。もちろん本研究会で論じられたジャーナリズムの問題とソトの知識への関心の問題は、それぞれに別の課題である。しかし、簡単には権力に屈しない開かれた知の養成という面では相互につながっており、ジャーナリズムや大学を含めた人々の不断の努力が求められることを改めて感じる貴重な機会となった。
高田 圭(法政大学国際日本学研究所・准教授)
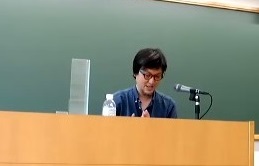 報告者:根津朝彦氏 |
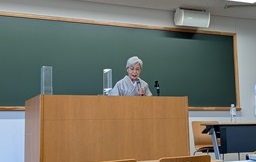 コメンテーター:田中優子氏 |
 司会:髙田圭氏 |

