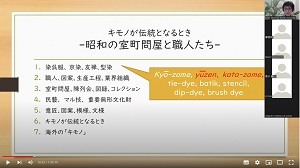【開催報告】国際日本学研究所主催 新しい「国際日本学」を目指して(14)公開研究会「キモノが伝統になるとき-昭和の室町問屋と職人たち-」2022年3月12日(土)2022/04/13
法政大学国際日本学研究所主催
新しい「国際日本学」を目指して(14)公開研究会
2022年3月12日(土)13時30分 ~15時オンライン(ZOOM)にて開催されました。
■報告者
岡本 慶子(法政大学経営学部教授・法政大学国際日本学研究所兼担所員)
■司会
山本 真鳥(法政大学名誉教授・法政大学国際日本学研究所客員所員)
■コメンテーター
田中 優子(法政大学名誉教授・法政大学国際日本学研究所客員所員)
***************
【開催報告】
昨年のHIJAS研究会「新しい『国際日本学』を目指して(10):海外における女性のキモノの表象」では、19世紀以降、キモノが海外において日本を示す記号として扱われるようになった経緯を学んだ。そこで今回は、同時期にそのキモノを生産する側にあった京都呉服業界から展望した。
明治維新で打撃を受けた京都の呉服業界は京都市と協力して技術開発に力を入れることとなった。力織機など機械の輸入をおこなった織物に比較して、江戸時代よりさまざまな染色技法が発達していた染物は、欧州から輸入した化学染料を利用して、独自に友禅新技法を開発し発展させた。新技法とは既に小紋染に利用していた和紙に柿渋を塗布した型紙を利用した多色捺染技法、つまり型友禅である。この型友禅が昭和戦前と戦後の2回にわたり呉服業界に染呉服のブームをもたらすこととなったのだが、立役者である室町問屋(特に染呉服商)と職人に焦点をあて、京都室町(業界の総称)の当時の活気を出版物や先行研究から推しはかり、現代に「伝統」と呼ばれているキモノが「伝統」と呼ばれるようになるまでを考察した。
明治時代になって庶民も絹の着用が認められるようになるが、式服、婚礼用裾模様などの手描き友禅は庶民には手の届かない高級品であった。19世紀後半の型友禅の開発により、手頃な価格でカラフルな模様染が可能となったが、大正時代になって徐々に着尺(アウター)に使われるようになっていった。型友禅に使われる「図案」は、それまでの織物や手描き友禅、その他の染物には無い、多色、リピートという「図案化」の技術が必要であり、古典柄、外来モチーフなどを取り入れながら、次々と新しい図案が作られ、商品が作られてきた。この図案作成から白生地の手配、工場への委託加工、技術援助、全国への流通を一手に担っていたのが室町問屋だった。
昭和初期には、金銭的に余裕ができ、おしゃれを楽しむようになる大衆は絹製品を好むようになっていったため、室町問屋は一般大衆に向けた型友禅の着尺を主流商品とするように生産を拡大していった。その一方で、高級手描き友禅の研究、開発にも力を入れた。高級友禅の展示会を開き、図録を出版したり、業界一丸となって見本市の開催や、染織祭り、宮崎友禅祭二百年忌など、さまざまな染織に関する祭事を行っている。さらに時代衣装の研究にも力を注ぎ、松坂屋、鐘紡、丸紅などは自社商品開発のための蒐集を始めている。戦後に人間国宝となる手描き友禅職人の上野為二もこの時期、父の工房で加賀友禅の研究を始めている。さらに、美術商の野村正治郎が江戸時代の小袖を利用した「誰が袖屏風」を制作し、図案家や染織家をターゲットとした図録を出版し始めたのもこの時期である。
これらのことから、室町全体として手描き友禅の高級品開発に力を入れ、友禅染めの格を上げたうえで、手頃な型友禅を普及させようという戦略だったと考える。友禅の下生地となる縮緬の生産量が増え価格が低下したことも重なって、友禅の生産量は昭和初期から増加を続け、昭和十年以降は年間500万反を超えた。染呉服を扱う室町問屋も京都商工人名録に記載されているだけでも明治後半から昭和十年代までに約3倍に増加していることからも、この時期友禅は売れ筋商品であったことがわかる。
室町問屋の流通網は既に全国に張り巡らされ、友禅は産業として成り立っていたが、それゆえに、友禅や友禅職人は、民藝や芸術とは一線を画し、「技術」「職人」として扱われた。それは、戦時下に工芸芸術保存資格者(丸芸)ではなく、工芸技術保存資格者(丸技)に指定されたことからも見てとれる。しかし、戦後、型友禅の技法が洋服地のプリントに応用された時、明治に開発された当時は「擬友禅」と呼ばれた型友禅は、はじめて「伝統の友禅」と呼ばれるようになった。それは開発してからのち、絶え間ない技術改良や図案の開発という職人の技術と、商品企画(意匠)に力を注いだ室町問屋の意匠力の協業で成し遂げられたことである。継続し、進化し続けたことで型友禅は伝統となったのである。
現代は、キモノを日常に着用する日本人はほとんどいなくなってしまったが、日本でも海外でもキモノへの興味がなくなってしまったわけではない。日本は世界に類を見ない染物の発達した国であることを忘れず、今、伝統と呼ばれている「もの」「こと」に固執することなく、今後も染物を発達させ、新たな伝統を作っていくことが望まれる。
【執筆:岡本慶子(法政大学経営学部教授・法政大学国際日本学研究所兼担所員)】